SEにキャリアチェンジしたkosumiです。
現在の会社に下積みのつもりで入社して3年。
居心地は悪くないですが、そろそろステップアップのために転職を考え始めました。
求人サイトを見れば3年前と変わらず、たくさんの募集があります。
今や募集要項に「システム開発経験1年以上」や「3年目安」とある会社にも、胸を張って応募できるようになりました。
つらつらと流し見していると、妙に待遇のよい求人に目を引かれます。
案件が選べる。年収50万以上アップ。
それは新SESをうたう求人でした。
SESはやめとけと巷でよく言われますが新SESなら……?
ということで、自分なりに調べてみました。
SE3年目が自分の転職先として考えたときのメリット、デメリットをまとめていきます。
忙しい人のために、先に結論だけ書いておきますね。
- SESは未経験者におすすめ、ただし大手を選ぶこと
- 新SESは実務経験1~5年の中堅SEにおすすめ、今後のキャリアを決めておくこと
- それ以降は自身のキャリアに合わせて選択
おさらい――そもそもSESとは?

全体の商流とSESの立ち位置

まずは上の図をご覧ください。IT系の仕事はこの流れが一般的です。
文章化するとこう。
- まずはソフトやシステムを製作したい会社が、どこかのIT企業に発注します。
- 受注したIT企業は、○○の技術は××の会社に依頼して……と技術領域に応じて細分化し、人を集めます。
- 集められた人は、それぞれの得意分野を生かして製作の一部を担当します。
と、このようなイメージです。
全体で見るとたしかに効率のいいやり方に思えます。
ですが、実際に派遣される側の視点で考えるとどうでしょう。
多重下請けという露骨なピンハネの構造になっていて、主に待遇面の不満がでてきます。
SESでの働き方
SES企業に入社すると、お客さんの会社(現場)に「SES企業の社員」として参加して作業することになります。
- SES企業に入社します。
- SES企業が、あなたのスキルや希望に合った「現場」を探してきます。
- 現場が決まったら、その企業に出向いて働きます。
- 契約期間が終わったら、また別の現場へ。
次は給料についてです。
SES企業の社員の給料は、入社したSES企業から支払われます。
その給料のもとになる報酬は、上流の会社から所属する会社に支払われています。
報酬は単価と呼ばれ、技術者のスキル×時間で決まっています。
自分の契約単価を教えてもらえるかは会社によります。
次はお客さんとの関係性について。
お客さんの会社との関係性は、準委任契約と呼ばれる形式が一般的です。
難しい用語ですが、要は「現場の指示に従って作業をすること」が仕事です。

SESを一言で表すなら技術者派遣。
派遣ですが、正確には派遣会社の正社員ということになります。
- 未経験でもチャンスがある
→お金をもらいながらキャリアチェンジの下積みができる - いろいろな現場を経験できる
→たとえば、入社難度の高い大手企業の環境で作業できる - 専門分野を究められる
→下流の方がプログラムを突き詰められる - 正社員になれる
→社会的信用が得られたり、次の契約までの待期期間にも給料が支払われる
- 現場ガチャになりがち
→希望の現場に配属されるかはタイミング次第。スキルアップできずに一生テスト要員ということも - 待遇があまり良くない傾向にある
→多重下請け構造なので、仕事に対して給与が安かったり過酷な現場に回されたりする可能性も - 孤立しやすい
→現場では外部の人扱いされて肩身が狭く、チーム参画でなければ自社の人とは接点がない
以上です。
もちろんすべてのSES企業がそうではないと思います。
たとえば大手のSESだと、新人が一人で現場へ送られるような可能性は低いでしょう。
ですが、とくに中小規模の余裕のないSES企業は上記のことを踏まえて求人をチェックすることが肝要です。
新SESとは?――従来のSESとの違い
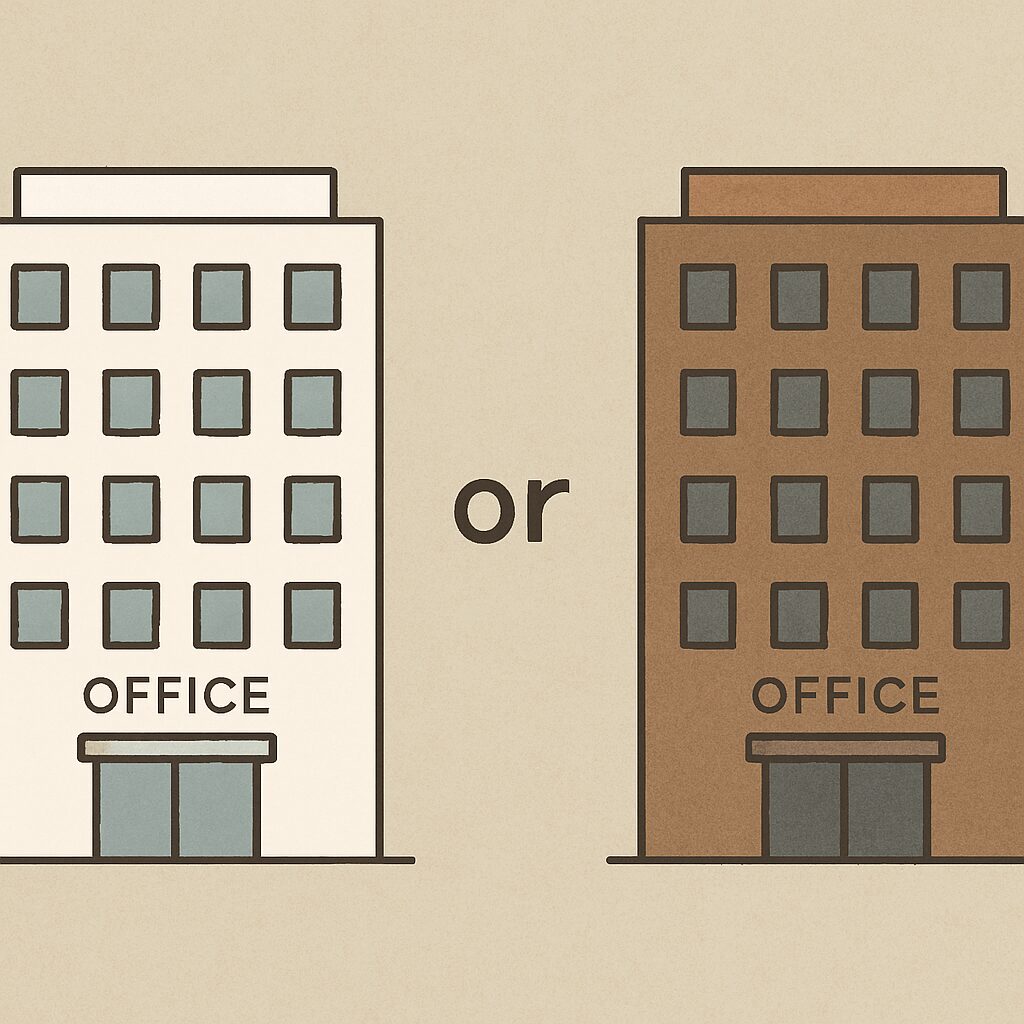
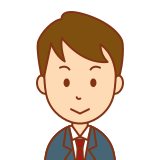
SESのデメリットでかすぎない? そりゃIT土方って呼ばれるわ

そこで登場するのが新SESです。
新SESとは、さきほどのデメリットを解消して新たに体制を整えたSES企業の総称です。
- 案件ガチャ問題の解消
→案件選択制度でエンジニア側が案件を選べる - 待遇の改善
→単価の公開や高還元(還元率70〜80%など)
案件が選べて単価も労働者側で確認できる。
待遇は正社員で、営業や経理などは会社に任せればOK。
新SESは一言で言うとフリーランスと正社員の良いとこ取りのようなイメージで、実際に新SES企業側ではそうしたイメージを売りにしている所もあります。
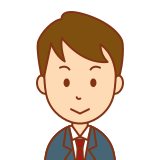
は? 最高じゃん! 新SESに転職するわ

と、思いますよね?
ここからは新SESの課題についてお伝えします。
- 新SESの問題点 > 従来のSESと比較した場合
入社には実務経験が必要
スキルが低いと結局案件を選べない - 新SESの問題点 > フリーランスと比較した場合
報酬の取り分はあくまで会社が決める - 新SESの問題点 > 正社員と比較した場合
稼ぎは自分のスキル次第
自分でキャリアを考えて学習を進めていく必要がある
従来のSESと比較した場合
誰でもOKな従来のSESと違い、新SESは経験1~3年を募集要項としている企業が多いです。
ある程度一人で稼ぐ力のある人、と言い換えることができるかもしれません。
仮に入社できたとしても、稼ぐ力が低い人には案件が来ません。
こちらが参画したいと思っても先方からお断りされてしまいます。
ですので、経験の浅すぎる人には新SESはまだ早いかもしれません。
フリーランスと比較した場合
SESは多くの場合、下流で予算が少ないです。
一から人を育てる余裕はないことに加え、利益確保のために粗利から会社に必要なお金を差し引きます。
当たり前のことですが、全部自分でやるフリーランスとはその点が大きく異なります。
ある意味で委託費とか外注費と考えてもいいかもしれません。
自分で取り分を決められないのは、会社員に慣れている人はともかく、フリーランス経験のある人からは不満が出るかもしれません。
正社員と比較した場合
自動的に昇給する正社員と違い、稼ぎは自分のスキル次第です。
だらだら働きたい人には向いてないでしょう。
加えて、通常の会社では自分のキャリアはある程度会社の業務内容に依存します。
案件が選べる分、何のスキルアップを目指していくかは自分次第です。
その他
なぜ高単価が実現できるのか
会社の取り分が決まっているからです。
新SESは、”あなたが稼いだお金”から”あなたにかかった経費”を差し引いた金額(=粗利)から、”会社の取り分”を引きます。
そして残りをあなたが給料として受け取るのです。
さらに言うと、新SESは交通費や社会保険料が”あなたにかかった経費”として扱われ、賞与の計算式で差し引かれます。
なので、遠方から通いになった場合などには、提示される年収から大きく下がるケースがあります。
あなたの給与 = (あなたが稼いだお金ーあなたにかかった経費) ー 会社の取り分
高還元を実現するために、会社は本社機能を最小限にしたり、テレワーク推奨して経費がかからないようにしたり、いろいろと工夫をしています。
なぜこれまでのSESは低単価だったのか(予想)
これは筆者の予想ですが、今までそうでなかった理由は、元請けと二次請け以降での予算の差がかかわってきているのではないでしょうか。
元請けでこのような高還元の方式にすると、会社の取り分が少なくなりすぎます。
たんに元請けが悪いという話ではなく、オフィスの維持などで必要な経費が多いからです。
だから元請けは従来の給与の支払い方式をとっています。
SESの場合は扱える予算に差があります。
元請けと同じ方式では、会社の利益確保を優先すると、デメリットが強く出すぎました。
SESは止めとけと言われていた理由はこのあたりでの情報でしょう。
そこで、会社の利益を確保しつつデメリットを解消するために、新SESと呼ばれる方式が登場したのではないかと考えます。
転職先としてみたSESと新SES

現在の35歳、SE3年目である筆者から見た、自分の転職先として考えた場合の超個人的な感想です。
転職の目的としては以下になります。
- 収入アップ
- 今後のキャリアアップが見込めること(PM/PL)
SES企業の場合

収入は大きく変わらない、キャリア的にもあえて転職する理由はないかな……
新SES企業の場合

収入アップが見込めるし、案件が選べるなら経験を積めるし検討の余地ありかも
追記:一度新SES企業様と面談をしたところ、収入アップは期待できる反面、年齢と経験を考慮すると筆者は案件を選べるほどの人材ではないようでした。残念!
まとめ
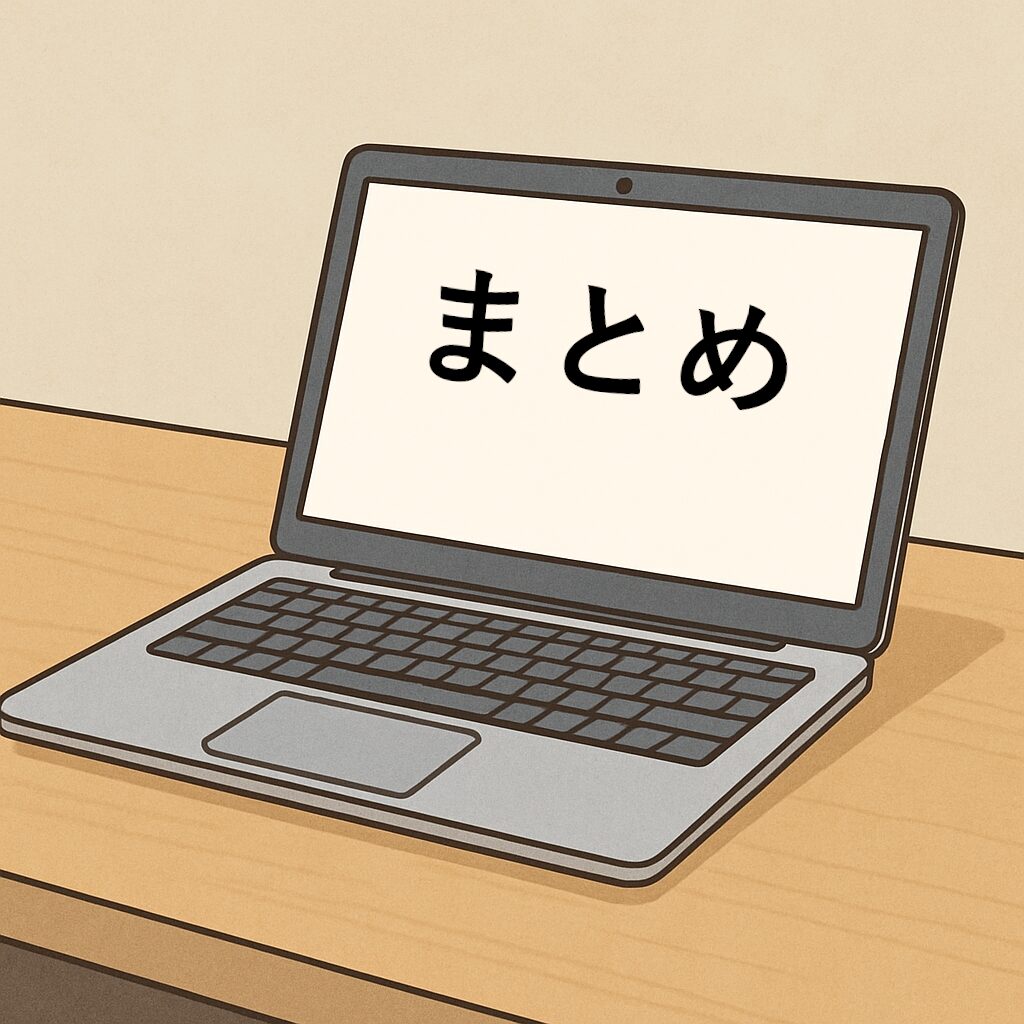
SESにしろ新SESにしろ、それぞれ向く人と向かない人がいます。
- SESは新卒以外で「未経験からエンジニアになりたい」という人
- 新SESは「ある程度のスキルが身につき、案件や単価を自分で選びたい」という段階になった中堅エンジニア
どちらも「正社員としての安心感」を持ちながらキャリアを積める働き方ですが、自分の目指すキャリアやライフスタイルに合った選択をすることが大切です。
大事なのは、「SESは悪い」というイメージだけで避けるのではなく、仕組みやリスクを理解したうえで選ぶこと。
そのうえで、自分がどんなエンジニアになりたいのか、どんな環境で成長したいのかを考えて、納得のいく転職活動を進めてください。
あなたのキャリアの一歩が、よりよいものになるよう願っています!
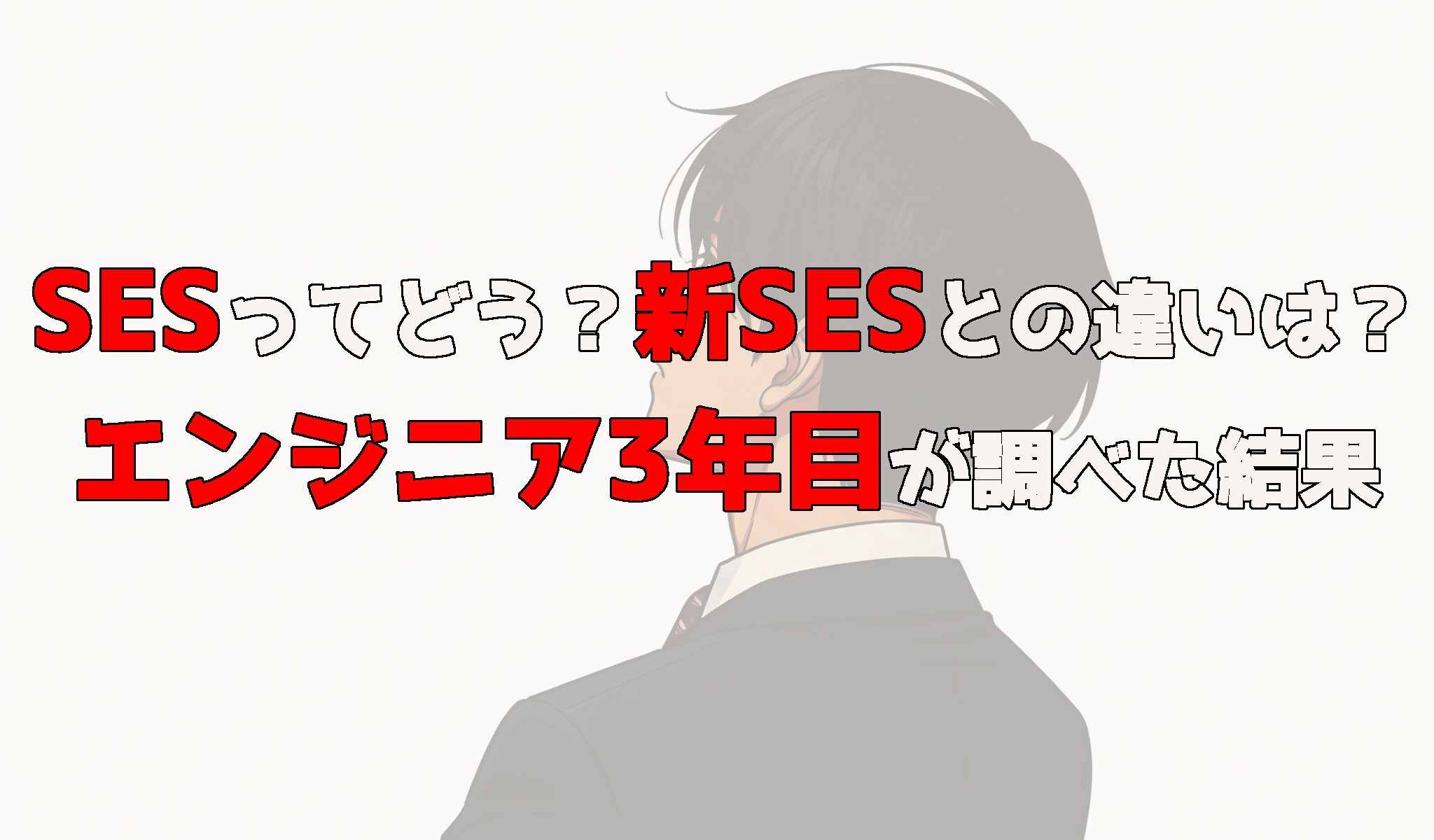
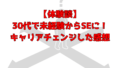

コメント