- AI時代のエンジニアの存在価値を知りたい人
はじめに
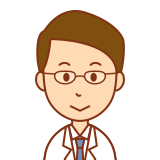
最近はAIがプログラム書いてくれる。
便利だけどもうエンジニアになる意味が分からない。

私もAIはよく利用していますし、進化が速すぎて不安な気持ちもわかります。
今回は私が職場や現場で聞いた実話をもとに、AI時代のエンジニアのあり方を予測しました。
- メーカーに就職しても調整業務が中心だったIT業界
- 技術力の重要性を理解した企業は理系の採用を増やしている
- AI時代に求められるエンジニアは「翻訳」
【過去】メーカー勤務だったエンジニアより――「調整」中心の業務
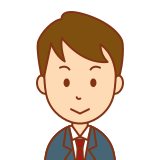
メーカーでの業務は協力会社との調整ばかり。
プログラミングとか技術的な仕事がしたくて転職した。
上記の話は、筆者が同僚から聞いた実話です。
メーカーに就職しても、技術力より調整するためのコミュ力が求められていました。
だからこそ、これまで筆者のような文系エンジニアにも出番があったと言えます。
では理系で情報を学んだエンジニアに未来はないのでしょうか。
ヒントはある作業員の方からいただきました。
【現在】メーカー協力会社の作業員より――採用は「理系院卒」
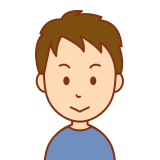
本社は理系院卒しか採用していないよ
上記の話は、筆者が現場で知り合ったメーカー協力会社の方から聞いた実話です。
これはコミュ力より技術力を重視する時代になってきた、という意味なのかもしれません。
では、これからの理系エンジニアは将来安泰なのでしょうか。
そして、文系エンジニアは不要になるのでしょうか。
理系で情報を学んだものの、非技術者の道を進んだ同級生に話を聞きました。
情報学部卒の非技術者より――理系の就職と文系エンジニア
まず理系エンジニアの道ですが、技術力のある理系が有利なのは間違いありません。
ただ理系進学しても適性がかなりあるとのことです。
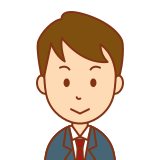
非技術者
適正に加えてかなり勉強もしないとついていけない。
俺は無理だと悟って非技術者の道を選んだ。
数学ができるか、ロジカルシンキングができるか、この二点が特に影響の大きい要素だそうです。
そうしたハードルを乗り越えた理系は、新卒から大手やメーカーを目指せます。
これは文系にはない、理系エンジニアの強みと言っていいでしょう。
ただ、それだけで通用するのであれば、今ほど文系エンジニアは多くなかったように思います。
理系エンジニアの弱点。
それは、「技術一辺倒でビジネス視点が欠けていること」です。
ただ高い技術力があればお金が生まれるわけではありません。技術力は誰かが評価して初めてお金になります。
だからこそ、これからのエンジニアはあなたの技術や成果物がどう人の役に立つかを常に意識していかなければなりません。
せっかく評価され始めた技術力ですが、「技術を究めただけ」で勝負するのであれば、強力なライバルが出現したからです。
皆さんもご存じ「AI」です。
これから先のエンジニアはどうなるでしょうか。
ここからは筆者の予測をお伝えしていきます。
【未来】AI時代に求められるエンジニアは「翻訳」

AIが人間を上回る日はもう目の前です。
将来AIの出力を理解するためには理系エンジニアの需要があるはずです。
AIの進化が世間に認知されはじめたのは、「アルファ碁」でしょう。
アルファ碁はプロに勝ったことで一躍有名になった、囲碁のAIです。
AIがプロを上回り、囲碁界はどうなったでしょうか。ここにヒントが隠れています。
人間のプロはいなくなったでしょうか。答えはNOです。
プロ越えを果たしたAIの放つ手はプロ棋士たちがこぞって研究して、その結果として今ではアマチュアにも広く普及しています。
将棋界の藤井聡太氏もそうですが、トップ層ほどAIを使った研究で棋力アップを図っています。
そして2025年現在、AIは他の分野でも人間を超える能力を発揮しはじめています。
先の例のように、エンジニアがいなくなることはありません。
AIの出力に対して研究したり、翻訳したりといった役割が生まれてくるでしょう。
コードやロジックの確認、非エンジニアへの説明やビジネス運用など、人ならではの仕事が無くなることはありません。
そうなったとき、理系的な専門の技術力+文系的な伝える力の両方を備えておくことが求められるはずです。

エンジニアの現場は、コミュ力に問題を抱える人が少なくありません。
ですが、できる人ほど技術力とコミュ力の両方を兼ね備えている印象です。
まとめ

これまではメーカーに入社しても業務は調整中心で、技術者志望の人材が離れてしまう歪な状態でした。
ですが、一部の企業では理系院卒の採用など、技術の価値が見直されてきているようです。
理系で情報を学ぶには数学や論理的思考能力が求められます。それなりにハードルは高いですが、新卒から大手やメーカーを狙える利点はあります。
理系のエンジニアには、研究一筋ではなくビジネス的な視点も持っておくことが求められます。
これは、AIの登場により、今後は専門的な技術「だけ」では太刀打ちできなくなるからです。
AIの出力を翻訳して人に伝えるような能力こそ、今後のエンジニアに求められるのだと考えます。
逆に文系エンジニアは、コミュ力・ビジネス的な視点に加えて技術力や知識を身に付けていかなければなりません。
ただのプログラミングであれば、すでにある程度はAIで代替可能だからです。
筆者も技術習得にAIを上手に活用して効率よく進め、時代に取り残されないようにしたいと思います。
以上です。
一緒に人生アップデートしていきましょう。
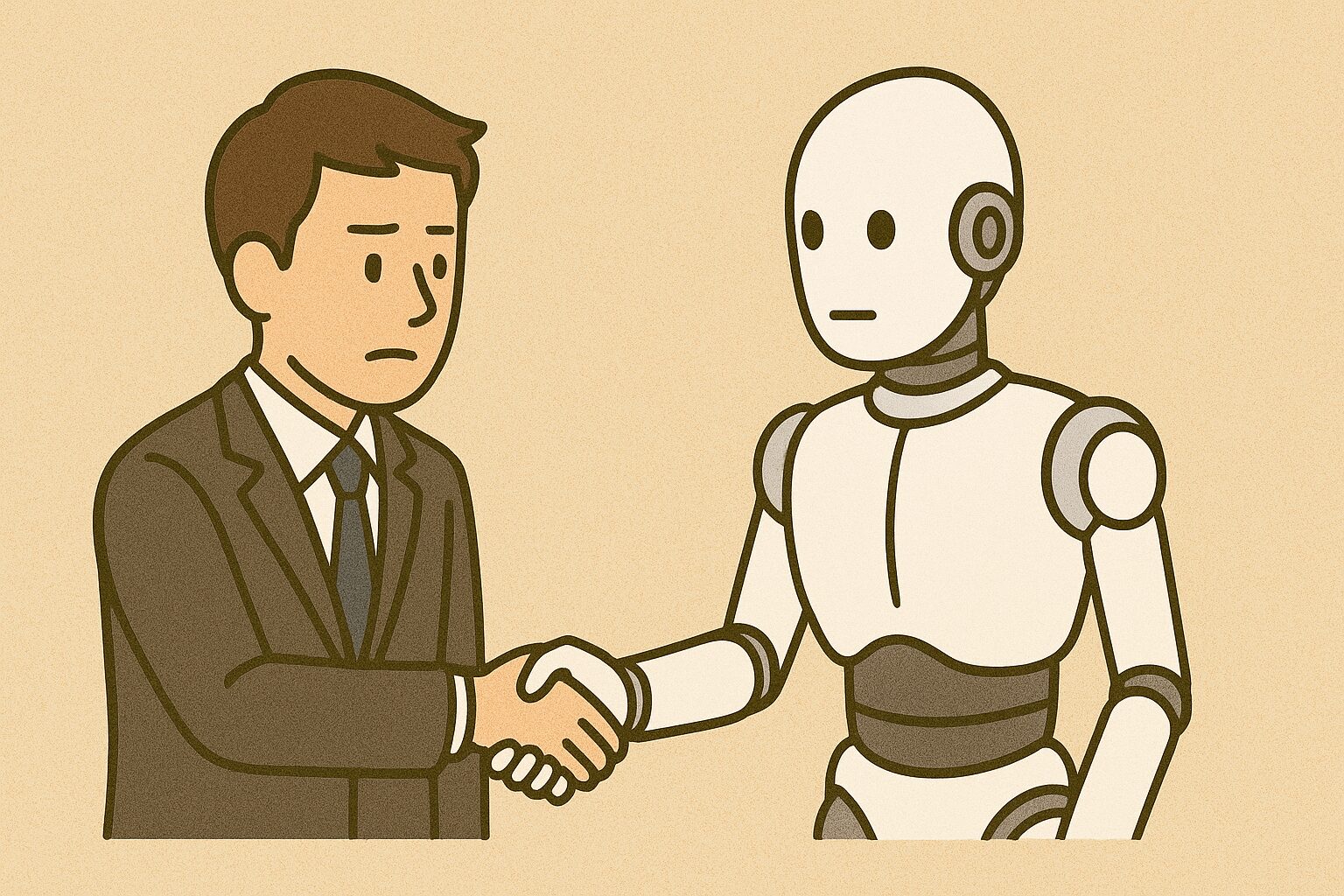


コメント